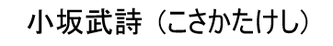高校受験用長文問題対策のためのブログで、英文解釈特訓の第15回です。やや難しめの英文を正確に解釈する練習をしましょう。
※今回は、指示語の内容を問う記述型の問題です。解法テクニックをしっかり覚えましょう。
※まずは、辞書や参考書などを一切使わずに自力で設問を解いてください。次に辞書や参考書などを総動員して自分なりの完全解を作ってください。その後で当サイトによる解説や正解を読んで答え合わせをしてください。また、自分の解答は必ずノート等に実際に書くようにしてください。
【 設問 】
次の文章を読み、下線部のitの具体的内容を日本語で書きなさい。
Many people believe success comes from luck, but others think hard work plays a more important role. In fact, those who try again after failure often learn valuable lessons that shape their future. Even small efforts, when repeated steadily, can lead to great achievements. This idea may seem simple, but understanding its depth takes time. Some people never realize the true meaning of it.

【 第1文の解釈 】
Many people believe success comes from luck, but others think hard work plays a more important role.
play a role = 役割を演じる(重要英熟語集第15集参照)
hard work を「熱心な仕事」と訳したらさすがにおかしいので、ここは文脈に合わせて少し工夫をしましょう。
きちんと訳すと、「成功は運によると信じる人が多いが、努力の方がより重要な役割を果たすと考える人もいる。」となります。
【 第2文の解釈 】
In fact, those who try again after failure often learn valuable lessons that shape their future.
in fact = 実際(重要英熟語集第15集参照)
those は、この文のように関係代名詞の先行詞として people の代わりによく使用されます。
failure = 失敗
lesson(s) = 教訓
that は lessons を先行詞とする主格の関係代名詞。
shape は、この場合「形成する」という動詞。
きちんと訳すと、「実際、失敗の後に再挑戦する人は、自分の将来を形成する貴重な教訓を学ぶことが多い。」となります。
【 第3文の解釈 】
Even small efforts, when repeated steadily, can lead to great achievements.
even ~ = ~さえ
efforts = 努力 これは第1文の hard work を言いかえていると考えられます。だからこそ、第一文の hard work は「努力」と訳すのが適切だということがわかります。
when や if のような when型接続詞の後の主語+be動詞は、意味が通じる範囲でよく省略されることを知っておきましょう。
She skips breakfast when ( she is ) busy. (彼女は忙しいときによく朝食を抜く。)
第3文では、when ( they (=small efforts) are ) repeated steadily というように they are が省略されていると考えます。
lead to ~ = ~につながる、~という結果をもたらす(重要英熟語集第15集参照)
きちんと訳すと、「小さな努力であっても、それがきちんと繰り返されることによって、大きな成果につながることもある。」となります。
【 第4文の解釈 】
This idea may seem simple, but understanding its depth takes time.
seem ( to be ) ~ = ~のように思える(英文解釈特訓第14回参照)
understanding は動名詞で「理解すること」
its は this idea を指しており、this idea は 第3文の "Even small efforts, when repeated steadily, can lead to great achievements." という考えを指しています。
depth は deep(深い)の名詞形で「深さ」
its depth は直訳すると「その深さ」となりますが、ここでは「深い意味」「本当の意味」「その本質」などのニュアンスであると解されます。
take は時間が「かかる」の意味(英文解釈特訓第14回参照)。
きちんと訳すと、「この考えは単純に思えるかもしれないが、その本質を理解するには時間がかかる。」となります。
【 第5文の解釈 】
Some people never realize the true meaning of it.
文頭の some は、英文解釈特訓第12回 で紹介した「(中には)~もある」と訳すパターンです。
realize = ①実現する、②悟る で、この場合は②の意味。
文末の it は、第4文の its と同様、第4文の this idea を指しており、より具体的には、第3文の "Even small efforts, when repeated steadily, can lead to great achievements." という考えを指しています。したがって、この文の the true meaning of it は第4文の its depth を言いかえただけだとわかるので、あえて第4文のときと同じように「その本質」と訳すのがよいでしょう。これは英文解釈特訓第7回で紹介したテクニックですね。
きちんと訳すと、「中には、その本質についに気づけない人もいる。」となります。
【 設問文の全訳 】
成功は運によると信じる人が多いが、努力の方がより重要な役割を果たすと考える人もいる。実際、失敗の後に再挑戦する人は、自分の将来を形成する貴重な教訓を学ぶことが多い。小さな努力であっても、それがきちんと繰り返されることによって、大きな成果につながることもある。この考えは単純に思えるかもしれないが、その本質を理解するには時間がかかる。中には、その本質についに気づけない人もいる。
【 設問の正解 】
冒頭で述べたように、この設問は、指示語の内容を問う記述型の問題です。このような問題の一番のポイントは、解答を自分の頭で作ってはいけないことです。必ず、本文からそっくり抜き出すことが鉄則です。
第5文の解釈で述べた通り、下線部の it は第4文の its と同様、第4文の this idea を指しており、より具体的には、第3文の "Even small efforts, when repeated steadily, can lead to great achievements." という考えを指しています。なので、実際の入試のときには、
Many people believe success comes from luck, but others think hard work plays a more important role. In fact, those who try again after failure often learn valuable lessons that shape their future. < Even small efforts, when repeated steadily, can lead to great achievements. > This idea may seem simple, but understanding its depth takes time. Some people never realize the true meaning of it.
という具合に、抜き出す部分を探し出して< >をつけるようにするのがコツです。
よって設問の正解は、「小さな努力であっても、それがきちんと繰り返されることによって、大きな成果につながることもあるという考え」となります。もちろん、最後は「~もあるということ」で終わってもOKですが、この it は同時に第4文の this idea も指していることをちゃんと理解していることを採点する側にアピールするために、「~もあるという考え」としておく方が得策です。
ところで、本問のような記述型の問題の採点基準は、いわゆるキーワード方式を採用するのが一般的です。本問の場合でいうと、
①「小さな努力」
②「きちんと繰り返される」
③「大きな成果につながる」
の3つがすべて書かれていれば正解。
という方式です。なので、決して解答を頭で作るのではなく、本文から探し出してきた< >の中を一言ももらさずに答案上にそのまま写すという姿勢が求められるのです。もしも、本問の場合に頭で解答を作ってしまうと、たとえば、「努力によって成果につながることもあるという考え」などという大雑把な解答になってしまい、内容的にはよさそうに見えても、上記①~③の採点基準によれば不正解とならざるを得ないのです。
このように、記述型の問題では、採点する側がどのような方法で採点をするのかということまで、きちんと知っておくことが大切です。